相続のことなら大阪府大阪市西区の『大阪相続支援室』へ。相続手続の専門家が相続登記 、遺産分割協議書作成、遺言書作成など相続の手続き全般をサポートします。
大阪の相続手続きの専門家
大阪相続支援室
運営:司法書士法人リンク(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
<大阪オフィス>〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1丁目4-2プライム本町ビル5階
電話での 受付時間 | 9:30〜18:00 (土日祝日は除く) |
|---|
アクリルパーテーションを 備えています。ご安心下さい。 | ご来所による面前相談を原則としております。 ご家族のご事情に応じて出張相談、テレビ電話相談(Zoom) などの対応をさせて頂きます。 |
|---|
遺言をしておいた方が良い場面とは?
どんな場合に、遺言をしておくとよいのでしょうか?
セミナーや相談会で遺言の有効性!?なんてお聞きになった方がいるかと思いますが、遺言はあらゆる場面で効力を発揮します。
例えば、
①夫婦二人で子供さんがいないとき、
②相続人が大多数となるとき、
③親が離婚や再婚をして前の配偶者の子供が居るとき、
④内縁の配偶者がいるとき、
⑤相続人間で感情的な対立や争いが予想されるとき、
⑥相続人の相続割合を調整しておきたいとき、
⑦息子の嫁や孫(つまり、相続人以外の人)に財産をわたしたいとき、
⑧相続人の中に判断能力を欠く者や行方不明者がいるとき等。
ここで整理して、お伝えしていきたいと思います。
遺言とは
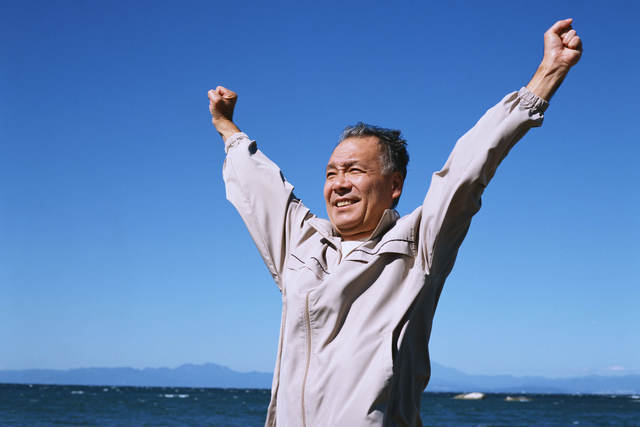
遺言とは、遺言者のご意思(誰に財産を渡したいかとか、相続分をどう決めたいとか、認知をしたいとか等、後に書いている事項です。)を、死後に実現するための制度です。
遺言は、親族を集めて口頭で伝えるだけではダメでして、書面を作成することが必要です。
その書面のことを、遺言書、「ゆいごんしょ」「いごんしょ」と言います。
法律上、遺言をすることが出来る事柄が決まっています(法定遺言事項)。
例えば、
①認知(民法781条2項)
②推定相続人の廃除・廃除の取り消し(民法893条、894条2項)
③祭祀財産の承継者の指定(民法897条1項)
④相続分の指定や指定の委託(民法802条)
⑤特別受益の持戻免除(民法903条3項)
⑥遺産分割方法の指定や指定の委託と遺産分割の禁止(民法908条)
⑦遺贈(民法964条)
⑧遺言執行者の指定や指定の委託(民法1006条)
これらの法定遺言事項以外に、感謝の気持ちや、相続人への心情などを記載することがあります。
法定遺言事項意外を書いたらダメだというわけではございませんので、「気持ち」を記載することは遺言をつくる上で、重要な役割を担っています。
遺言をしておいた方が良い場面2-1
①夫婦2人で子供がいないケース
まず、「相続人」の検討からしますと、ご夫婦の間にお子様がいなければ、「親」が第二順位で相続人になります。
その「親」が他界していたら、第三順位で「兄弟姉妹」が相続人になります。
昨今、高齢化が進んでしますので、70代の方のご両親が90代でご存命というケースは、普通にあると思います。
ここでは、兄弟姉妹が相続人になると想定します。
(遺言で生前準備していない時。つまり、遺産分割協議をしなけらばならない時。)
ご主人が亡き後、奥さまは、ご主人側のお兄さま、お姉さまと相続について話し合い(遺産分割協議)しなければなりません。
奥様は、良好な関係のご主人サイドの兄弟なら、話し合いもスムーズに進むでしょうが、親族関係が悪化しているとか疎遠であれば、「遺産分割をしたいので、この書類に実印を下さい!」なんて言いにくいですよね。
ましてや、相続財産が「自宅不動産」ならば、絶対はんこをもらわなければ、住めません(住みにくい)ですよね。
こういった、懸念があるなら、ご主人が元気な生前に「私のすべての財産は、妻に相続させる」旨の遺言書を準備しておくべきです。
また、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言が効果的です。
「子供がいないケース」が、遺言が最も効力を発揮する!といわれています。
さらに、「夫婦が互いに」遺言を書いておくのが良いかと思います。
②相続人が大多数となるとき
相続人が大多数になるのは、子供がおらず兄弟姉妹が相続人になり、さらに代襲相続がおこっているようなときや、親世代の相続関係が未分割のまま放置されているときに、相続人が大多数になります。
(もし遺言書がなければ・・・)全国に散らばった相続人間で遺産分割の協議をしなければなりません。
昨今では、日本全国ならまだ良いほうで、世界各国に相続人が散らばるケースも出て参ります。
世代も違えば、考え方も違う多数の相続人と話し合い(遺産分割協議)をすることは至難の業です。
このようなときに、遺言書で準備をされることをおすすめいたします。
被相続人がどの財産を誰に相続させるのかについて遺言書を書いておけば相続人間で話し合う必要もなく、各相続人の負担を軽減することが出来ます。
遺言をしておいた方が良い場面2-2
③親が離婚や再婚をして「前の配偶者の子供」が居るとき

前の配偶者(前妻)のお子様に相続権はあるのでしょうか?
もちろん、有ります。
前妻の子供にも、現在の子供と全く同じ相続権がありますので、前妻の子供を相続から排除するわけにはいきません。
ですので、自宅などの前妻の子供に渡せない財産があるのなら、今の配偶者の子供に相続させる遺言書を準備しておくべきです。もし、遺言書を準備していなかったら、前妻の子供からはんこ(ご実印)を頂戴しにあがるということになってしまいます。
もちろん、前妻の子供は、遺留分がありますので、遺留分を請求されたら、それに従うことになります。
ただ、この際も、遺留分で請求される「財産の順番」を遺言書で決めておけばご自宅を守ることは可能になります。
④内縁の配偶者がいるとき
内縁の配偶者は、相続権がありません。日本の民法はあくまで法律婚が前提となっています。
ですので、このケースで法定相続人は、ご主人サイドの「親」か「兄弟姉妹」になります。
内縁の奥様に住居を確保したいなら、遺言書で準備されることをおすすめします。
もし、互いに連れ子がいるなら、養子縁組もされておくべきです。
⑤相続人間で感情的な対立や争いが予想されるとき
相続人となる兄弟同士が仲が悪く、すでに争いの火種があるようなときは、遺産分割をめぐっても争いがしょうじるであろうことは容易に想像できます。
また、奥様(配偶者)とご主人サイドの兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹)が相続人となるときも、争いになるときがございます。
このような場合には、遺言書を準備して、誰に何を相続させるのか、またどのような考えでそうしたのかを遺言書に記載しておけば、相続争いをある程度防ぐことが出来ます。
⑥相続人の相続割合を調整しておきたいとき
これは何かといいますと、相続人の一人がすでに自宅購入資金の援助を受けているので、相続割合を減らしたいとか、相続人の一人にはずっと介護をしてもらっているので、相続割合を増やしたいとかのご希望があるときの例が当てはまります。
この場合に、遺言書で何の準備もしなければ、相続割合は法定通りの平等になります。
そうなれば、それに不満を持つ他の相続人から「寄与分」や「特別受益」の主張がされて争いが生じてしましいます。
その際に、どのような考えで「相続割合」を変更したのかを含めて遺言書で準備しておけば、熾烈な相続争いは避けられるかと思います。
⑦息子の嫁や孫(つまり、相続人以外の人)に財産をわたしたいとき
「相続人」を考えますと、このケースでは、息子の嫁、孫は相続人には当てはまりません。
しかし、息子の嫁には介護でお世話になったとか、孫はかわいいので、しっかり大学進学できる資金は渡してあげたいとかの希望があったとします。
この場合に、遺言書で何も準備しなければ、「法定相続人」でほかの方に財産がわたってしまいます。遺言書で、準備することをおすすめいたします。
⑧相続人の中に判断能力を欠く者や行方不明者いるとき等
例えば、姉、兄(認知症)、弟(行方不明)が相続人となるケースで、実際、姉しか財産の管理ができないが、兄と弟を排除して遺産分割をすることはできません。
この場合に、兄については成年後見人などを選任する必要があり、弟については不在者財産管理人を選任する必要があります。
これらをすべて姉が手続きするのは、負担が大きいです。
このケースで、姉に全財産を相続させる遺言書を書いておけば、少なくとも相続の段階では、成年後見人の選任や不在者財産管理人の選任は不要となりますので、相続人の方のご負担は軽減できます。
ご予約はこちら
ご相談内容は、相続手続き全般でしょうか?不動産の名義変更のご相談でしょうか?
来所のご予約は、お気軽にお電話ください。
お電話もしくはお問合せフォームより、ご予約してください。
※ご高齢者の方、お急ぎの方は電話にてご予約ください。

来所ご予約は、
お気軽にお電話ください
- 相続手続き全般、不動産の名義変更、預金ん解約手続きを相談したい?
- 遺言書作成や成年後見、家族信託の相談をしたい
- 無料相談を受けてたら、依頼をしないといけないのでしょうか?
いえ、そのようなことはございません! - 無料相談時には、何をもっていったらよいでしょうか?
- 事務所に行って、書類を見せながら相談したい
- 土曜日は相談にいけますか?
- 「本日、息子(主人)が休みを取ったので、急ですが、予約を取れますか?」
あなたさまからのご予約をお待ちしております。
受付時間 : 9:30〜18:00 (土日祝日は除く)(予約面談は土曜日も可能です)
※お急ぎの手続き(ご高齢者の方、緊急の遺言、遺産相続、不動産の名義変更など)
にも最大限対応させて頂きます。
※フォームからのお問合せは平日も土日祝も24時間受け付けています。
電話予約は、
こちらからどうぞ。
ご高齢者、お急ぎの方はこちらからお電話ください。
コロナの5類移行に先立ち、2023年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断に委ねられています。

ご予約は、電話・メールにて受け付けております。
ご面談のご予約は、こちら
9:30〜18:00
(土日祝日は除く)
事務所紹介

司法書士法人リンク
(旧 司法書士法人渡辺総合事務所)
代表者 : 渡邉 善忠
大阪オフィス
TEL :06-6136-3751
〒550-0004
大阪府大阪市西区靱本町
1丁目4-2プライム本町ビル5階
アクセス:本町駅から100M




